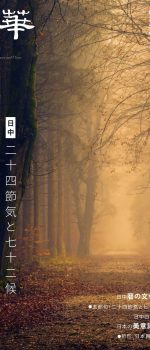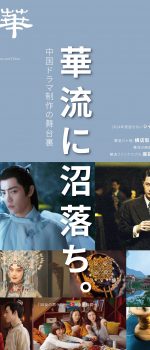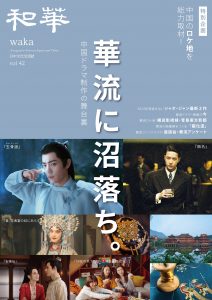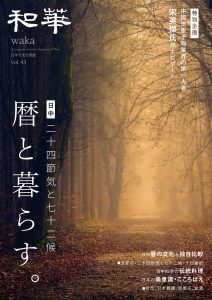
ようやく秋の気配を感じるこの季節、私たちが使う「立秋」や「秋分」といった言葉は、太陽の周年運動に基づいて一年を区分する「二十四節気」の名称として親しみ深い。しかしさらに節気を三つの候に分けた二十四節気七十二候となると、すべての言葉が思い浮かぶ人は少ないのではないだろうか。二十四節気は中国人が考案し、日本に伝えられた農業を行う上で欠かせない知恵であり、現在も四季折々の風物や習慣と共に私たちの日常生活に深く根付いている。今号の『和華』では、中国初の気象予報士であり、数々の二十四節気にまつわる書籍も出されている宋英傑氏に日中の二十四節気を紐解いていただいた。後半では日中両国の四季の伝統料理、日本の美意識や心を表現する和菓子や飾り、日本舞踊を通してみる二十四節気、四季を彩る盆栽などをご紹介している。ぜひ今号が暦暮らしを楽しむきっかけになれば幸いである。